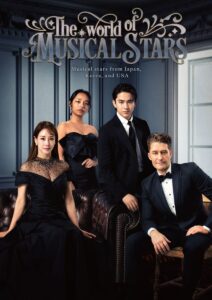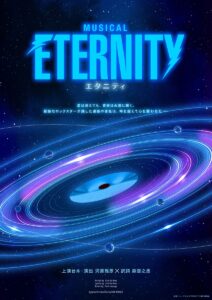6月6日(月)にシアタークリエで開幕した『ラディアント・ベイビー~キース・ヘリングの生涯』。誰もが目にしたことがある印象的なアート作品を生み出し、31歳の若さでこの世を去ったキース・ヘリングの人生を、ロックやポップス、パワフルなダンスで紡ぐオフ・ブロードウェイ発のミュージカルだ。
初日の前日となる6月5日(日)に本作のゲネプロと囲み取材が行われた。今回はゲネプロの模様をレポートしたい(一部ネタバレあり)。
関連記事:『ラディアント・ベイビー~キース・ヘリングの生涯~』演出の岸谷五朗にインタビュー!「自分の人生をすべて“突っ込む”つもりで創っています」

1988年、ニューヨーク。ポップアートの世界で売れっ子となったキース・ヘリング(柿澤勇人)は、押し寄せる仕事の中、自分が本当に創りたいものが何なのか分からなくなっていた。恋人のクラブDJ、カルロス(松下洸平)ともすれ違いが多くなり、友人の写真家、ツェン・クワン・チー(平間壮一)との約束を反故にすることもしばしばだ。キースが心を開くのは、アトリエに絵を習いに来ている三人の子どもたちだけ。アシスタントのアマンダ(知念里奈)はそんなキースをどう扱っていいのか分からない。
キースと彼を取り巻く人々の思いが錯綜する中、子ども時代から現在まで、キースの過去がフラッシュバックしていく・・・。
通常の舞台の上に、ゆるいスロープ付きの変形ステージが置かれている。そこに登場するのは作品の案内役となる三人の子どもたち。彼らの歌う「THIS IS THE WORLD」で物語は始まり、1988年のアトリエと過去とが交差しながら進行する。

一幕で最高にパワフルなのが、ディスコ「PARADISE」のシーンだ。クワンに連れられ夜の街に繰り出したキースは、そこでかけがえのない存在・・・カルロスと出会う。二人のエネルギーとディーバウーマン&ディーバマンの圧倒的な歌声、喧騒の中で踊り明かす人びとの熱気とがミックスされ、非常に高い熱量を生み出すこの場面は、ミュージカルを見ているというより、ライブに参加しているような感覚だった。
関連記事:ミュージカル『ラディアント・ベイビー~キース・ヘリングの生涯~』主演の柿澤勇人にインタビュー!「これでダメならすべてやめようと覚悟して稽古場に行きました」

本作で主役のキースを演じる柿澤勇人は、田舎からニューヨークに出てきた戸惑い、自分が創りたい作品が何なのか分からなくなる焦燥、そして自らの死を意識してからの疾走感と、実在したアーティスト、キース・ヘリングの人生を繊細&パワフルに魅せる。近年では『デスノート The Musical』や『サンセット大通り』、蜷川幸雄演出作品『海辺のカフカ』と、どこか達観していたり、当事者である自分を第三者的な目線で見ているキャラクターを演じることも多かった柿澤だが、『ラディアント・ベイビー』のキースは常に感情が揺れ動き、それを時に爆発させる役どころ。それを見事に演じ切った・・・いや、ギリギリまで自らを追い詰め生き抜いた姿に大きな拍手を贈りたい。

キースの恋人・、カルロス役の松下洸平は、小悪魔的な悪さと傷付きやすい内面とを混在させた造形で魅力的に役を立ち上げる。カルロスの孤独は、アートに関してクワンのようにキースと分かり合えないところから来ているのだと非常に明確に伝わってきた。

“セックスをしない男友達”と自らを称するクワン役の平間壮一。平間演じるクワンが、とことん優しくキースを包み込む様子はピュアの一言。そして弾ける汗の中、華麗に踊る姿は誰よりもパワフルだ。キースとクワンとが死を目の前にし、白い衣装を着て静かにジョークを交えながら語る場面では涙が止まらなくなった。

こういう文章を書く上で「観るべき」というセンテンスを使うのは全く本意ではないのだが、本作の持つ熱量と胸に突き刺さる痛み、人が生き・・・そして創造していくことの辛さと素晴らしさ・・・死と向き合う姿・・・それらをぜひ一人でも多くの人に劇場で体感して欲しいと切に思う。

ミュージカル『ラディアント・ベイビー~キース・ヘリングの生涯~』は、6月22日(水)までシアタークリエにて上演中。東京公演終了後は6月25日(土)~26日(日)に森ノ宮ピロティホール(大阪)にて上演予定。なお、シアタークリエ内のホワイエでは「キース・ヘリングポスター展」も開催中。
(取材・文 上村由紀子)