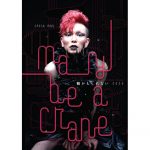「観劇初め」というのは、その年の演劇ライフの行方を占うようでなんとなく意識してしまう。2020年1月9日(木)に、EPOCH MAN(エポックマン)新春ひとり芝居『鶴かもしれない2020』が東京・下北沢 駅前劇場にて開幕する。この作品を取材したいと思ったのは、この作品を“目撃した”という記憶を、新しい年と共に一人でも多くの人と共有したいからかもしれない。
「EPOCH MAN」とは、鴻上尚史が主宰する虚構の劇団所属の俳優・小沢道成による個人演劇ユニットだ。2013年に立ち上げ、人の心・・・特に女性の心の中に眠る感情を、繊細に、一方で執拗に突き詰め、観る者の心を“演劇”の魔法で包み込む。『鶴かもしれない』というこのひとり芝居は、これが3度目の上演。最初は2014年5月(明大前 KID AILACK ART HALL 5F Gallery)、2016年1月(下北沢OFF・OFFシアター)・・・この過程を観ていたからこそ、駅前劇場に進出する姿を追ってみたいと思った。

取材をしたのは、美術制作真っ只中の頃。この日の小沢は、何やらしょんぼりしていた。繰り返しになるが、これは彼の個人ユニット。舞台美術も、稽古も、ずっと一人なのだ。理由を聞いてみると、舞台美術を作るのに必要な資材が350個だと思っていたら、なんと計算違いをしており450個必要だということが分かったそう(実際は約550個必要だった模様)。一人の制作現場では、間違えるのも自分、それをカバーするのも自分。そんなリアルも、包み隠さず見せてくれた。
この「EPOCH MAN」の歩みにも、小沢道成という俳優のリアルが映し出されている。もともと「自分の名前を広めるため」「仕事を待つだけではいたくない」という気持ちから始めたユニットだったそうだが、やっていくうちに「作も演出も企画も美術も制作もやる、トータルプロデュースの楽しさ」に傾倒してきたという小沢は「今はそういう気持ちしかないんです」と(この瞬間は、うっかりミスのことも忘れられたのか)気持ちのいい笑顔で笑いながら、再再演についていろいろと語ってくれた。

ここで、『鶴かもしれない』という物語のことをざっくりと説明しておこう。タイトルから察せるとおり、ベースとなっているのは「鶴の恩返し」。この昔話の舞台を現代に置き換え、東京の繁華街の片隅で出会った、一人の女と一人の男の物語とし、小沢と3台のラジカセと10着の着物を使って表現する。
この表現に至るまでには、2つの出会いがあった。京都で活動していた頃、ある俳優と出会った小沢。その人の名前は、田中遊(正直者の会)。“四次元演劇”をコンセプトに、「儀式」というほぼ一人芝居と、「戯声」という複数人でのパフォーマンスを2軸として活動する俳優だ。小沢は、田中の作品の中で、ラジカセを使った脳をテクニカルに動かす表現スタイルに触れ、「僕もやってみたい!」と強烈な憧れを抱いたという。
もう一つは、高畑勲監督作品の映画『かぐや姫の物語』に触れたこと。かぐや姫が十二単を脱ぎ捨てながら、すべてを投げとうとする姿を、ダイナミックかつ儚く描いたシーンに触れ、誰もが知る話を別のものにリンクさせ、演劇的に“リアレンジ”できないかという発想が湧いたそうだ。
こうして、刺激を受けた様々な要素を小沢の中に取り込み、生まれたのがこの『鶴かもしれない』だった。もともとは、一回きりの実験的な上演のはずだった。しかし、思った以上に観客がおもしろがってくれているという手応えがあった。
そんな2014年の初演を「あの時の僕が必死に書いたものだから、あれでよかったのかもしれないけれど」と、小沢は振り返る。「僕の中で、この話は最初、悲劇だったんです。でも、改めて考えてみたら、登場人物たちが抱いていた夢や理想をもっと描いた方がただの悲劇ではなく、物語として濃いものになるかもしれないと思ったんです」そうしてたどり着いたのが、2016年の上演だった。

再演で変わっていたのは、男性側の描き方。初演では、女性側の面だけで物語が描かれていったが、再演では男性の職業が明確にされていたり、どういう人物なのかが分かるようになっていた。
「そうすることで、女性が抱いている気持ちの理由や行動の動機が深くなるかもしれない、と思ったんですよね。今回も、女性側も男性側も、今の僕が足りないなと思った部分を足しました。俳優としても、人間としても、大事にしたいキーワードがあるんです。この感覚は、『鶴かもしれない』の中でもマッチすると思うので、美術や演出面にも足してみています」。
今回のバージョンが正解なのか?それは分からない。足りなかったと思うのは、二度と戻れない時間の中での出来事だ。初演も再演も、当時の小沢にしか作れないものだったし、これから見せてくれるものは今の小沢にしか生み出せないものであり、同じ時間を生きる観客しか享受できないものになるだろう。前にしか進まない時間の中にある、“演劇”のおもしろさ。

創り手の感覚も大きいが、演劇はハコ(劇場)が変わることで受ける影響も大きい。もともと小沢は、今回の再再演を再演と同じOFF・OFFシアターで2週間やろうとしていたそうだ。しかし、ある人から「OFF・OFFシアターで一度このひとり芝居は成功しているんだから驚きがないよ。駅前劇場でやりなよ」と背中を押され、劇場と相談し、今回の挑戦に至ったという。
「劇場さんに電話をして『駅前劇場でやれる可能性が僕にはありますか?』と聞いたら、快く貸してくれて、夢を応援してくれたんです」。この「駅前劇場でやる」ということが、舞台美術の制作にも大きな影響を与えていた。


ここで、冒頭の小沢をしょんぼりさせていた舞台美術の話に戻る。無数にあった細い木材は「枠」として使用される。この枠は、アクリル板に取り付けられることになっていた。なぜ、アクリル板なのか?「キラキラ輝いている時ほど、自分がどういう顔をしているか確かめることが大事なんじゃないかなって思うんです」。

壁一面にアクリル板を張った「壁」はツヤツヤと輝き、小沢が浮かべる感情の機微も、それを見つめる観客の表情も、すべてを背景にぼんやりと映すことになる。そして、驚きの仕掛けもたくさん。この舞台美術が物語にどんな影響を与えるのか。小沢の話を聞いているだけでワクワクしてきた。劇場に行って実践してみるまで、意図していることがうまく実現できるか分からないと言っていたが・・・きっと、うまくいく気がする。
しかし、公開してくれた舞台美術の模型を見ても、初演、再演とかなり違った印象だ。日本の昔話のモチーフとはかけ離れた、海外作品のような印象すら受ける。以前、小沢は本作を「いつか海外で上演してみたい」と発言していた。その気持ちの、現在は?
実は、この駅前劇場での公演のあとに、小沢は横浜公演を予定している。タイトルを『Maybe a Crane ~鶴かもしれない~』とし、TPAM(ティーパム)–国際舞台芸術ミーティング in 横浜に参加するのだ。TPAMとは、舞台芸術に携わる国内外のプロフェッショナルが様々な公演プログラムやミーティングを通じて交流する場。
こちらは、駅前劇場での演出とはがらりと姿を変え“原点”に立ち返った上で、新しく“映像”の演出を取り入れることを明言している。「海外の方の目に止まったらいいな・・・。僕、海外でやりたいという夢は今も持ち続けていますよ」と、語る小沢の目はキラキラと輝き、創り途中の木材片を映し出していた。
“かもしれない”は原動力。「いつか本多劇場でもやってみたいけど、ラジカセを使う演出上、この駅前劇場がギリギリのキャパかもしれないし、次にやるのは海外かもしれない」。

夢と欲。小沢が生み出す作品を見ていると、美しい物語の中にその表裏一体の顔がのぞく。今回、アクリル板を張った反射する「壁」は、「扉」にもなり「窓」にもなるそうだ。その根底にあるのは、「自分から開けていく」という意識。小沢は、今回のようにひとり芝居を通して自ら次の扉を開いていくし、窓を開けて新しい空気が流れ込んでくるのを待っている。
EPOCH MAN 新春ひとり芝居『鶴かもしれない2020』は、2020年1月9日(木)から1月13日(月・祝)まで東京・下北沢 駅前劇場にて。
『Maybe a Crane ~鶴かもしれない~』は、2020年2月10日(月)から2月16日(日)まで横浜・yoshidamachi Lilyにて。
(取材・文・撮影/エンタステージ編集部 1号)