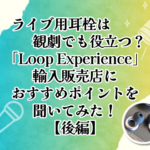劇団スタジオライフの最新公演『TAMAGOYAKI~Time Ago Year Key~』が7月13日(土)より東京・中野ウエストエンドスタジオにて開幕した。このほど舞台写真とオフィシャルレポートが到着したのでお届けする。
同作は、作・演出の倉田淳のオリジナル作品で、1990年にかつて小劇場界の登竜門と謳われた「パルテノン多摩小劇場フェスティバル」で最優秀賞を受賞。ファンタジックな手ざわりを残しつつ、流れゆく歳月の中で人が生きることの悲しさや温かさを描いた珠玉の1本だ。それを今回、11年ぶりに上演する。2019年の今、卵焼きの甘くてふんわりとした味わいは、人々の心にどんなふうに残るのだろうか。

どうして大人になると子どもの頃の想い出があんなにも眩しく、そして切なく映るのだろう。毎日が楽しくて、自分の凡庸さとか、世の中の不公平さとか、そんなことに憂う時間があるぐらいなら、早く家にランドセルを置いて、友達と遊びに行きたかった。
日が暮れるまで泥んこになって、家に帰ったらおいしいゴハンをお腹いっぱい平らげて、お風呂に入って、布団にもぐりこめば、あっという間に眠ることができた。日々は、そうやって続いていくものなのだと、何の疑いもなく、そう思い込んでいた。
でも、大人になると違う。自分は、まったく特別じゃないこと。未来は、決して明るいばかりではないこと。布団に入ってもなかなか寝付けない夜もあるし、てるてる坊主をつるしたって明日が晴れになるわけではないことも、とっくの昔に知ってしまった。
そんな“こんなはずじゃなかった”大人たちがもう一度何者でもなかった子ども時代に帰ることができたなら――『TAMAGOYAKI~Time Ago Year Key~』はタイムスリップを題材としたヒューマンファンタジーだ。

主人公は、とあるぼったくりキャバレーで客引きをしている時男(トキオ)、翔(カケル)、蟻巣(アリス)という3人の幼なじみ。人を騙して金を巻き上げるような毎日に、彼らはすっかり夢も希望も失ってしまっていた。
そんな3人は、ある夜、店にやってきた博士と名乗る怪しい初老の男性と知り合ったことから、このどうしようもない現状から逃れるべくタイムスリップを決意する。行き先は、人生でいちばん楽しかった時代。目覚めた彼らがいた場所は、自分たちの少年時代。そこで時男たちは、小学5年生の自分たちと再会する。

グリコの箱。オルガンの音。だるまさんがころんだ。げんこつやまのたぬきさん。そして、お母さんがつくってくれたお弁当の卵焼き。少年時代に登場するモチーフの数々はどれも普遍的で、観客をそれぞれの子ども時代へと一緒にタイムスリップさせてくれる。
けれど、その中で思い出していくのだ。決して子どもの頃だっていいことばかりではなかったことを。むしろ純粋だった分残酷で、愚かだった分、取り返しのつかない罪を犯してしまうこともあった。
小学5年生の時男たちは、ちょっとトロい同級生の真似木に対し、イジリとイジメの危ういラインで接していた。まったく悪意がなかったと言えば嘘になる。あの頃の子どもたちは自分より弱い者に対して、とても攻撃的だ。そして、やってはいけないと言われると、ついそれを破りたくなる。無邪気すぎる好奇心が、一生消えない後悔を生むことも知らずに。
そんな少年時代の光と影を描きながら、物語はクライマックスへと進んでいく。浮き彫りになってくるのは、「人はいくつになっても夢を見ることができるのか」という問いだ。こんなところで一生を終えたくないとくすぶっていた大人の時男たちは、過去の自分と対峙することで、自分の人生そのものと向き合うこととなる。
てるてる坊主をつるしたって、明日が晴れになるわけないと、もう大人の僕たちは知っている。じゃあどうして子どもの頃の僕たちは遠足の前の日にあんなにもいそいそとてるてる坊主をつくっていたのか。それは、その心に夢見る力があったから。

紙飛行機だって同じだ。今、紙飛行機をつくれと言われても、すっかり折り方さえ忘れてしまった。でも、最初に紙飛行機を飛ばしたとき、すーっと前に向かっていくその姿に、確かに心が沸いたのだ。下手くそすぎて、ほんの数メートルでぽとりと地面に不時着したけど、がんばればもっともっとどこまでも遠くへ飛んでいけるような気がした。
キャバレーの女の子に相対性理論について演説をぶつ博士は、まるで空気が読めない変人だ。でも、博士は今も一心に紙飛行機を折り続けている。どこまでも遠くへ飛んでいけと。その夢見る力がグリコの箱をタイムマシンに変えたのだとしたら――
博士と出会った3人が最後にどんな結末に辿り着くのかは、劇場で確かめてほしい。けれど、最後に時男が見せたあのマイムは、「何か夢中になれるものを見つけたい」とこぼしていた大人たちが取り戻した夢見る力なんだと、そう思った。

スタジオライフというと、オールメール(全員男優)で耽美な世界という印象が強いが、ここ何作か拝見してきて、改めてそれだけではない球種の豊富さを実感している。本作も耽美というよりは、むしろ泥臭くパワフルだ。特に中野ウエストエンドスタジオという小空間では、そのエネルギーがダイレクトに観客に伝わってくる。
中心的な人物である時男を演じたのは仲原裕之。2008年の上演でも、仲原はこの時男を演じていた。俳優は11年分の時間と経験を重ねたが、役は年をとらない。演じる上では、きっと難しい部分もあったことは容易に想像できる。けれど、歳月を重ねた分、より人生の苦みを知り、少年時代が遠くなった分、より憧憬は膨らんだ。
時男という男の器用そうに見えるのにどうしようもなくうまくいかなかった人生を、時にコミカルに、時にセンチメンタルに表し、多くの人が共感を寄せられる人物像として時男を構築した。翔役の若林健吾の気弱さと優しさの混ざり合わさったような笑みや、蟻巣役の宮崎卓真の華やかさとなめらかな台詞回しもいい。
そして、見事なパワープレイを見せたのが博士役の藤原啓児。2014年からスタジオライフの代表を務める、文字通り劇団のコアだが、ここではベテランの貫禄をかなぐり捨て、少年のような博士の童心をハイテンションな演技で体現。酸欠になりそうな長台詞を、若手を圧倒するような熱量でこなし鮮烈な印象を与えた。

『TAMAGOYAKI~Time Ago Year Key~』は7月28日(日)まで東京・中野ウエストエンドスタジオにてMayerチームとJouleチームのWキャストで上演(本稿は、Mayerチームの上演をもとに執筆)。
もうすぐ子どもたちは夏休みだ。かんかん照りの夏の陽射しに目を細めるたび、夢中になって遊んだ子ども時代が恋しくなる人は、ぜひ劇場に。ノスタルジーに浸りながらも、明日を生きる力をもらえる時間となるはずだ。
【公式サイト】http://www.studio-life.com/stage/tamagoyaki2019/
(取材・文/横川良明 写真/オフィシャル提供)