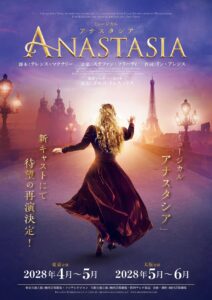46st.側劇場出口
2017年6月12日(月)に授賞式が行われる第71回トニー賞で、作品賞を含む12部門でノミネートされた『ナターシャ、ピエール・アンド・ザ・グレート・コメット・オブ・1812』(『Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812』)。マルチアーティストのジョシュ・グローバンのブロードウェイデビュー作としても話題を集めているミュージカルを、ニューヨーク、インペリアル劇場で観劇してきました。

46st.側の壁に埋め込まれていた劇場プレート。
ロシア人作家トルストイの小説「戦争と平和」第2巻第5部を基につくられた『ナターシャ、ピエール・アンド・ザ・グレート・コメット・オブ・1812』(以下、『ザ・グレート・コメット』)は、2012年にオフ・ブロードウェイで幕を開けた後、一旦幕を下ろし、2016年11月より再びブロードウェイで上演されています。
時は1812年のモスクワ。若く活発なナターシャは、ナポレオン戦争に出兵しているフィアンセ、アンドレイの帰りを待っていました。彼女はモスクワのゴッドマザー、マリア D.の元で過ごしますが、その間に、悪名高いプレイボーイのアナトーリに誘惑されてしまいます。しかも、アナトーリは既婚者。その事実を知らぬまま、どんどん恋に落ちていき、ついには駆け落ちにまで発展。マリア D.は旧友でもあるアナトーレの義理の兄・ピエールに助けを求めます。そこからこの駆け落ちの真相が明らかになり、アンドレイとナターシャに悲劇が起こります。

劇場入口前の歩道に埋め込まれていた『レ・ミゼラブル』のプレート。
まず劇場に入って驚くのが、ここが本当についこの前まで、『レ・ミゼラブル』を上演していたインペリアル劇場なのだろうかということ。19世紀のロシアのレストランに足を踏み入れてしまったかのように、深みのある真紅のカーテンが劇場内を囲い、当時を彷彿させる絵画の数々がその上を覆います。インペリアル劇場が大改装されて『ザ・グレート・コメット』の世界が出来上がっていました。
この新たな劇場空間には一般的な“ステージ”が無く、客席と客席の間がステージ、つまり、演技スペースと言った方が正しいほど、劇場空間全体を使って上演されます。劇場全体を出演者が駆け回り、演じ、踊り、演奏するので、観客とキャストの距離が近い分、スピード感、スリリングさをより感じられました。

『ザ・グレート・コメット』のPLAYBILL
また、この作品の魅力の1つがロック、ポップ、ソウル、フォークソング、エレクトロニックダンスミュージック、ブロードウェイ音楽などをミックスしたという楽曲の数々。今の今まで、当時の帝政ロシアを彷彿させるような民族調の曲が流れていたのが、一瞬にしてポップになり、テクノ音楽へと変わっていくのです。そのため、眼前で繰り広げられていた物語の色合いも帝政ロシア風のものから現代のクラブ風な雰囲気へと一気に飛びます。音楽なしでは、この作品が成立しないほど、大きな要素となっていました。次々と変わっていく音楽がスピーディーな作品をさらに加速させていきます。
ハイスピードで進んでいくこの作品を、観客は「観劇する」というより、演者と共に踊り、音を奏で、楽しみ、この場の空気を創り上げていくと表現した方がふさわしいかもしれません。全体に流れる享楽的な空気を楽しむ作品。あっという間に2時間半が過ぎていきます。

劇場入口扉
もちろん、ただ騒いで終わるだけではなく、核になるのは息を飲む大波乱の物語。
ピエールを演じたのは、前述のジョシュ・グローバン。この物語のカギを握る人物ですが、主に、ストーリーテラーのような立ち位置。力強い語りと歌で物語を引っ張り、盛り上げていきます。彼の存在が、この作品のスピーディーな展開の中にも引っかかる節を作っていました。若く美しいナターシャを演じたデニー・ベントンは、愛嬌があって可愛らしい若手女優。素直に喜び、ときめく姿が初々しく、観客もその姿に虜になるほど。ジョシュと同じく、デニーにとっても本作がブロードウェイデビューとなりました。ナターシャと恋仲になるアナトーリは、ルーカス・スティール。ナターシャを誘惑する役ということもあり、その演技には腹黒さが見え隠れし、キャラクターの根にある悪が滲み出ています。ナターシャのゴッドマザーであるマリア D.を演じたグレース・マクリーンは、母親の代理として、翻弄されるナターシャをピタリと叱りつけます。教育者のような芯の通った演技を見せました。

45stからの劇場外観
物語の大筋は、ナターシャは婚約中のアンドレイを差し置いて、アナトーリと駆け落ちしてしまうというもの。ここで起こることは背徳行為。しかし、この世界を音楽が享楽的に盛り上げます。この盛り上がりが、一般的、常識的に許されざることだとしても、やりたいようにやれば良いと述べているような気もしました。
(取材・文・撮影/大嶽なつき)