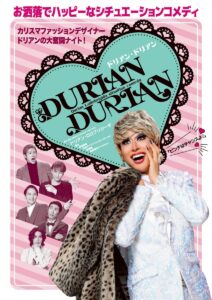2024年11月29日(金)、堂本光一主演『Endless SHOCK』が東京・帝国劇場にて大千穐楽を迎え、2000年から続いてきた『SHOCK』シリーズが有終の美を迎えた。大千穐楽公演でのカーテンコール及び、終演後の囲み会見の模様をお届けする。
フィナーレを迎えた堂本光一のライフワーク『Endless SHOCK』
『SHOCK』シリーズのラストイヤーとなる2024年も、堂本光一は記録を打ち立て続けた。4月22日に大台の2000回上演を達成。5月9日の夜公演では、森光子が舞台『放浪記』で1961年から2009年にかけて積み上げた国内演劇の単独主演記録2017回を超え、2018回を達成。さらに、9月28日に博多座にて、単独主演記録2100回という前人未到の記録を達成した。
最後の11月公演が開幕した際、堂本は初日会見で「『SHOCK』自体も終わりが見えていても最後までもっとよくするために千秋楽までやっていくと思います。何のためにするのか、もうそこに答えはないんですよね。幕を開けたらお客様がいる、ステージに立って振り返れば素晴らしい仲間がいて、オーケストラピットにも素晴らしい奏者の皆さんがいて。そういった皆さんのために頑張ろうという気持ちがすべてじゃないかなと思います」と、本作のテーマである“Show must go on”の精神を語っていた。そうした思いのもとに24年間、走り続けた作品がついに最後の瞬間を迎える。
今回の大千穐楽の模様は、47都道府県100カ所の映画館でライブビューイング上映を実施。公演3日前の26日には、チケット完売に伴い急きょチケット追加販売が実施されるという異例の事態に。いかに多くのファンが、この作品を愛してきたのかが伝わってくる。
大千穐楽カーテンコールには、主演の堂本光一をはじめ、ライバル役を務めた上田竜也、長年作品を支えてきたふぉ〜ゆ〜の福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介、4月から全公演に出演してきた松尾龍、11月から参加となった最年少の松浦銀志、オーナーの娘リカ役の綺咲愛里、オーナー役の前田美波里が登壇した。
2024年を彩ったキャストが集結!カーテンコールレポート

全国の映画館も含め、7万人以上のファンが最後のステージを見守った大千穐楽のカーテンコール。ステージ上には、本作に出演したキャスト陣に加え、前日千穐楽を迎えたリカ役Wキャストの綺咲愛里、9月公演でライバル役を務めた佐藤勝利をはじめ、寺西拓人(4月公演)林翔太(7・8月公演)、室龍太(7・8・9月公演)、高田翔(4・7・8・9月公演)、原嘉孝(7・8月公演)、島田歌穂(5・7・8月公演)が駆けつけた。
「もう喋ることはございません」という堂本光一の言葉から始まったカーテンコールだが、約1時間たっぷりとキャストの思いが語られていくこととなる。全2128回、今年だけで142回も上演された本作。数字を目の当たりにすると、改めて『SHOCK』の異次元すごさが伝わってくる。
毎回千穐楽が嫌いだと言っている堂本は「大千穐楽ともなると、本当に大大大嫌いなんですよ。でも全国7万人の皆さんに見守っていただいてすごく励みになりました」と、観客への感謝の言葉を述べた。
恒例の花束贈呈では「ちょっと重いので持っていられません」というほどのずっしりと豪華な花束が堂本に手渡され、くす玉から「光ちゃんお疲れ様でした」のメッセージが現れると同時に客席には銀テープが降り注ぐ。
ここからはキャスト1人1人が、『SHOCK』への並々ならぬ思いを、ときに涙混じりに語っていった。
トップバッターは上田。「2003年、この場所で 『もう出るな』と言われた『SHOCK』にもう1度戻って来るとはまったく考えていませんでした」というと、堂本と当時を再現する場面も。コロナ禍での公演中止も経験した上田は「エンターテインメントとはなんだろう。お客様、そしてファンの方に喜んでもらえることはなんだろうと、もう一度深く考えさせられました。自分の中ですごく深い作品になりました」と振り返った。
帝国劇場に駆けつけた佐藤は「僕は『SHOCK』、そして光一くんの背中を観てエンタメのすべてを学んできました。『Endless SHOCK』の文字通り、光一くんの背中を追い続けてきた僕たちの胸にこの作品の思いは響き続けますし、教わったものを大事に進んでいきます。悩んだのですが、最後はお祝いの言葉で締めたいと思います。光一くん、おめでとうございます」と、実に彼らしい真面目なコメントを述べる。
堂本から「短めでね」と釘を差されて次にバトンを受け取ったのはふぉ~ゆ~の4人。随所に笑いを散りばめながらも、この作品と歩んできた歴史が長いグループとあって、涙を滲ませていた姿が印象的だった。

19歳から出演しているという越岡は「心残りはリカ役ができなかったこと」と冗談を飛ばしながらも「やっぱり寂しいですね。明日も帝国劇場に来てしまいそうです」としんみり。「いつも通りを意識したけど、今日はちょっと無理でした」と語るのは福田。舞台裏で堂本が見せた“いつもとは違う千穐楽ならではの行動”の数々を暴露すると、客席のあちこちからすすり泣く声が聞こえてきた。
福田自身も涙を浮かべながら、「最初からもうずっと『(泣いたら)いかん、いかん』という気持ちでやってきました。素晴らしい背中を見せていただいてありがとうございました」と最後は深々と頭を下げた。
辰巳は1番覚えている台詞として「コウイチ」をピックアップ。「僕らが世界一『コウイチ』を言いわけられる“七色のコウイチ”を持った男たちです」と光一愛を覗かせ、「5年ぶりに帰ってきましたが、いつも通りの僕らと光一くんの時間が特別で大切で。もう先輩の主演舞台に4人揃って出るのはこれが最後かもしれない。その思いの中で、光一くんの背中を特等席で観ることができて幸せでした」とコメントした。

ふぉ~ゆ~のトリを務めるのは、堂本の次に『SHOCK』に出演してきた松崎。松崎は一言発する度に肩を震わせ、落ちそうになる涙を必死に堪える。その姿を見た堂本は「マツはムードメーカーでいつもヤイヤイ言っているけど、実はふぉ~ゆ~の中でも1番繊細で。隠れたところですごく支えてくれた」と、長年の相棒に感謝を伝える。さらに感極まってしまった松崎が「終わりは始まりなので・・・僕は始まります!」となんとか言葉を紡ぐと、周りからは「38歳まで始まらなかったのかぁ」とツッコミが入り、よりいっそう和やかな雰囲気となった。
過去に一度『SHOCK』のオーディションに落ちているという2024年公演皆勤賞の松尾龍は、11月公演で出番が追加された屋上のシーンでの思い出を語り「作品に関わることができて幸せでした」。

11月から急きょ出演となった最年少の松浦銀志は上田も見学していたオーディションの思い出を回想。堂本から「あの期間であれだけのものを覚えて、すでに出来上がっているカンパニーに入るプレッシャーは大変だったと思う」とねぎらいの言葉をもらうとポロポロと涙をこぼしてしまった松浦。カンパニー全員が親のように優しい表情で松浦を見守る場面が印象的だった。
原や寺西、高田、林、室らも、それぞれの思いと感謝を堂本へと伝え、パフォーマンスで長年に渡り作品を支えた石川直は「またどこかでご一緒できたら嬉しいです」と挨拶。


ヒロインのリカ役を務めた綺咲は「この作品での出会いは本当にかけがえのないもので、これからも長く胸に留めておきたい大事な思い出です」と心境を語ると、中村はこの作品で2つの夢が叶ったと告白。1つ目は「今の帝国劇場に立つこと」、2つ目は「憧れていた女優さんがやっていた役をやること」だという。堂本が「神田沙也加さんだよね」と言葉を添えると、中村は「大きな夢を叶えてくださって、この瞬間を皆さんと共にさせていただいて、どう言葉に表していいかわからないのですが、感謝の気持ちでいっぱいです」と涙をこぼした。


オーナー役の島田はこの作品を「人生の宝物」と表現。「光一さんの背中を忘れません」と涙ぐみ、11年本作に出演してきた前田は「涙が止まらなくなってしまいました」と大千穐楽を振り返った。続けて「2013年から光一さんの大ファンになりました。そして、この作品のファンになりました。ですから、私は皆さんと同じ気持ちなんです。この作品がなくなってしまうことは、すごく寂しい。ですが、この作品で長い時間を過ごさせていただけたことの感謝は、私にとっては役者としての宝物です。光一さん、どうぞこの作品を超えるいい作品をまた作ってください」と、座長へのエールを送った。
それを受けた堂本は、長年積み重ねたこの作品を超えるものを作るのは大変なことだとしたうえで「『SHOCK』専用劇場でも作ってやればいいか」と提案。客席からは期待を込めた大きな拍手と悲鳴が上がる。
まだ上演できていないメンバーでの『Eternal』も観てみたいこと、コウイチ役を誰かに受け継いでもらえたら嬉しいと思っていることなど、大千穐楽を迎えた今だからこその話も飛び出た。「ファンの方にとったら複雑な思いもあることだというのも理解しております。でも、このコウイチという役を24年間演じるにあたって、“ステージに立つ人間の究極系”みたいなものをコウイチで描いてきたんですよね。その究極体を演じるというのは、辛い24年間でした。だって僕は全然究極じゃないんだもの。技術といったものはそんなにありませんから、役に負けないために何ができるかというと、気持ちしかないんですよ。その気持ちをずっと維持し続けるっていうのはね・・・いや、これは頑張りました、自分でも」と、コウイチ役と歩んだ24年間を振り返る。
さらに「今日観たものが皆さんの心の中で思い続けてもらえる作品となったなら、『SHOCK』はずっと生き続けていくと思うので、ぜひ思い浮かべていただければ嬉しいです」とファンへのメッセージを述べると共に、作品を支えてきたキャストやスタッフへの感謝とねぎらいの言葉を送った。
湿っぽい雰囲気になるかと思いきや、堂本はすかさず「24年間で1番衰えたなと思ったこと」を暴露。「暗くなった瞬間に捌けるっていう動作が遅くなった」と明かし、ステージ上で衰えっぷりを再現してみせると、劇場は笑いに包まれた。さらに、取り壊されるセットの所有希望者を募り、盛り上がる場面も。
最後に「このカンパニーは今日ここで解散して、それぞれの場所でまた活動が始まります。僕もみんなを追っていきたいなと思っておりますので、皆さんも応援よろしくお願いします。というわけで、24年間、本当にありがとうございました」と、笑顔でカーテンコールを締めくくった。
『SHOCK』は「永遠」、堂本光一囲み会見レポート

終演後、撤収作業が進む劇場にて、改めて堂本光一の囲み会見が実施された。
どこかスッキリとした表情で登壇した堂本は、「今ここに来るまで劇場の袖を通ってきたんですが、撤収って本当に早いです。もうかなり撤収されていて、みんな早く『レ・ミゼラブル』(※次に帝国劇場で上演される)にしたいみたいです(笑)」と、約3時間の公演に約1時間のカーテンコールを終えた直後とは思えない、いつも通りのキレのあるトークと爽やかな笑顔を浮かべた。
レポーターからの「泣きましたか?」という質問には「いいえ、芝居以外では全然泣いていないです。それよりも本当にやり切って、背負ったものを下ろせたと思ったんです。思ったんですけど、もっと重たいものが乗りかかってきたような気もします」と胸の内を明かす。新たに感じた重さの正体は分からないとしながらも「僕が作るエンターテイメントを、お客様も、共演者のみんなも欲してくださっている。そんな空気を感じました。でも、自分が舞台に立つことをやめるわけでもないし、『SHOCK』の幕は下ろしましたが、いつも通り活動していきます」と続けた。
新たな舞台に話が及ぶと「まだ構想には至っていない」とのこと。一方で、自分の夢として「自分が積み上げてきた『SHOCK』という作品を表から観てみたい」と語り、後継者に作品を引き継ぐことにも前向きな様子を見せる。レポーターが「光一さん以上のフライングをする人を観たことがない」とコメントすると、「現れないでしょうね(笑)。いやいや、冗談です。記録にしてもそういったものにしても、破られるためにあるものですし、自分としても破ってほしいです」と、茶目っ気たっぷりな言葉のなかに舞台への熱い思いを滲ませる。
具体的な構想はまだないとのことだが「自分のエンターテインメントを通じて、お客様があれだけ幸せな顔をしてくれるっていうのは、舞台以外ではないのかなと思えるくらい素敵な空間なんです。それを今後も作っていけたらなと思います」と、未来への意欲は十分の様子。
ファンにとっても気になるのは、カーテンコールで飛び出した「『SHOCK』専用劇場を作りたい」という発言ではないだろうか。実現可能性については「まだ分からない」とのことだが、「1日2回公演がなければ専用劇場で毎日できます!」と笑顔を見せた。
「作中で好きな台詞は?」という質問には、『Endless SHOCK -Eternal-』の「それは思い続ければいつでもそこにいる」というオーナーの台詞を挙げた。『SHOCK』本編ではセリフとしては登場していないが、ずっとこの言葉が胸にあったそう。「このメッセージはいろんな形にあてはめることができると思うんです。いなくなってしまった人のことを思うことや、舞台という儚いものを記憶として留めておくこととか。思いって人を瞬間的に強くすることもあると思いますが、実はそこよりも思い続けていくことが大事なんじゃないかと、常に意識してきたポイントです。この作品にしても、共演者やスタッフ、お客様、そういったみんなの思いの集合体が舞台の世界になるし、いろんな人生に当てはめることができるメッセージだと思います」と語った。
改めて堂本はこの作品を振り返り、「もうすぐ46歳。寿命の半分くらいまできたわけですが、この『SHOCK』ですべてを経験させていただいたと思っています。これから先の人生、『SHOCK』以上に刺激的なことがあるのだろうかって考えると、もうないと思うんですよ。あるかもしれないけど、そう思うくらい全てを経験させてもらった気がします。天災やコロナ禍もありました。その都度、エンターテイメントを届けるためにはどうすればいいのかとやってきたわけですが、そう考えると、もう(これ以上のことは)起こってくれるな。起こらない方が幸せなんだろうと思います。だけど、ここで学んだことは絶対に生きてくるだろうと。この24年間、今だったら止められちゃうようなことも無茶をして強引にやってきた部分もありましたが、それをやれたことも含めて幸せでした」と思いの丈を聞かせてくれた。
最後に「光一さんにとっての『SHOCK』とは?」と問われると、「難しいな・・・」と言葉を選びながら「永遠。今後にも期待を込めて、永遠であってほしいです」と、24年間の『SHOCK』の歴史に最後の言葉を添えた。
(取材・文・撮影/双海しお)