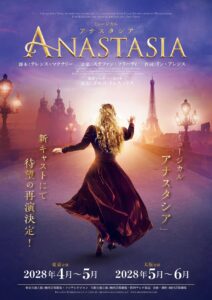2020年9月4日に東京芸術劇場プレイハウスで藤田俊太郎演出ミュージカル『VIOLET』日本キャスト版が開幕した。本作は、梅田芸術劇場が英国チャリングクロス劇場と共同で演劇作品を企画・制作・上演し、演出家と演出コンセプトはそのままに「英国キャスト版」と「日本キャスト版」を各国それぞれの劇場で上演する日英共同プロジェクト第一弾で、唯月ふうか、優河が主人公・ヴァイオレットをWキャストで務め、成河、吉原光夫、spi、横田龍儀、岡本悠紀、エリアンナ、谷口ゆうな、稲田ほのか、モリス・ソフィア、畠中洋、島田歌穂らが出演。一度公演中止になるも、一部内容を変更して3日間のみの限定上演が決まった本作の公開ゲネプロの模様をお伝えする。
本作を手掛けるのは新進気鋭の演出家・藤田俊太郎。ロンドン公演は単身渡英し現地のキャスト・スタッフと共に作品を創り上げ、オフ・ウエストエンド・シアター・アワードで6部門にノミネートの快挙を果たした。大好評を博したロンドン公演に続き、当初2020年4月に上演が決まっていた日本キャスト版だったが、コロナ禍で公演が全て中止に。しかし、9月4日(金)から3日間、一部内容を変更しての奇跡の公演が実現した。

物語は1964年、アメリカ南部の片田舎で生まれ育ち、幼い頃に父親による不慮の事故で顔に大きな傷を負い25歳の今まで人目を避けて暮らしていたヴァイオレットが、その傷をいやすべく奇跡のテレビ伝道師に会いに旅に出かけるところから始まる。西へ1500キロ、人生初の旅。長距離バスに揺られながら、ヴァイオレットはさまざまな人と出会い、多様な価値観を知り少しずつ変化していく姿が描かれている。バスに乗客が乗り込みながら重ねていく歌声、メロディーがこれからのヴァイオレットの長い長い旅路に向けての希望と決意を感じさせる。
ヴァイオレットは想定していたよりも気が強く、はっきりとした物言いをする女の子だった。同じバスに乗り合わせていた黒人の兵士・フリック(吉原)が途中立ち寄ったバーで差別を受けていたらモノ申すし、“同情心”からうちに泊まっていけばいいと声をかけてくれる老婦人(島田)の誘いはきっぱりと断る。しかし顔の傷から卑屈な感情が育ち、自分は“傷つくプロ”だと自負し、たまに他の人の痛みに鈍感になる。

現在軸の物語と共に、幼少期のヴァイオレット(稲田ほのか、モリス・ソフィアのWキャスト)と今は亡き父(spi)の回想も展開されていくが、その頃のヴァイオレットと今のヴァイオレットは、“成長”で言えばそんなに変化はないのかもしれないと感じた。卑屈になって、傷を見られて恐れられたり同情するのが怖くて内側に引きこもったっきりだったから。
それでもテレビ伝道師の“癒しの力”を信じて一歩踏み出したヴァイオレット。伝道師への思いを馳せる場面だけは無邪気な乙女なようでかわいらしいけど、その口から語られる夢は現実味がなくて痛々しい気持ちにもなる。一方でどこか雰囲気が父に似ているフリックに惹かれつつも、分かりやすくアプローチしてきて一緒に居て気が楽なモンティ(成河)とも関係を深める、そんな女性の弱さと強かさ持ち合わせている。物語が進み、ヴァイオレットがさまざまな価値観に触れることでヴァイオレットに付随するものが増えたり、そぎ落とされたりする。そこにこの旅の意味があるように感じた。

力強く、それでいて寂しさや切なさを含んだ歌声とメロディー、回り舞台の盆と舞台上にある3台のカメラ。多角的にそのヴァイオレットの姿を捉えていくことが出来るおかげで、その機微や世界観の広がりを感じることができた。人は多面性があって、どの角度で物事を捉えることが出来るかで人生が変わっていく、そんなことを改めて認識できたような気がする。この長い旅路を見届ける頃には、観客の気持ちにも何か変化が起きているかもしれない、と思える作品だった。
ミュージカル『VIOLET』は9月6日(日)まで東京芸術劇場プレイハウスにて上演。公演時間は約2時間だ。
【公演情報】 https://db.enterstage.jp/archives/413
(取材・文/エンタステージ編集部 3号 写真/オフィシャル提供 撮影:花井智子)