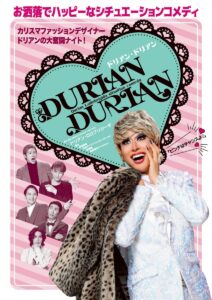2018年2月20日(火)、東京・シアタートラムで開幕した『岸 リトラル』。本作は、レバノン生まれで内戦を経験した作家ワジディ・ムワワドの作品で、麻実れい出演で日本でも二度上演され数々の演劇賞を受賞した舞台『炎 アンサンディ』を含む4部作の第1作目にあたる。そのゲネプロの模様をレポートする。
ムワワド作品に、演出・上村聡史、翻訳・藤井慎太郎が再び集った。また俳優も『炎 アンサンディ』に続き岡本健一、栗田桃子、小柳友が出演し、そこに中嶋朋子、亀田佳明、大谷亮介、鈴木勝大、佐川和正が加わる。

『炎』は“母と子”の物語だったが、『岸』は“父と子”の物語だ。ウィルフリード(亀田)は人生最高のセックスの絶頂の時に、電話で父の訃報を告げられる。ほとんど会ったことのない父イスマイル(岡本)。母(中嶋)はウィルフリードを産んだのと引き換えに命を落とした。

それ以来、父は世界を巡る旅に出てしまった。死体安置所で父に対面し、その亡骸を母と同じ墓に入れたいと願うウィルフリードだが、何故か母の親族たちに大反対される。一体、父と母に何があったのか?ウィルフリードは父の遺体を背負って埋葬先を探す旅に出た。死を受け入れられない父の亡霊とともに・・・。

二人が目指したのは父の故郷。そこは内戦の跡が濃く、人々はたくさんの死と悲しみと怒りを抱えている。どことははっきり描かれていないが、中嶋の華奢な身体から唸るように出る低い歌声が、一気にここを中東のどこかにする。
亡霊を演じる岡本が、時間を追うごとに目に見えて腐っていく様子もおもしろい。細身の亀田の身体が、ウィルフリードの現実感の希薄さや、頼りなげな雰囲気を増長させる。


旅をするウィルフリードたちはいろいろな人に出会うため、亀田と岡本以外の役者たちは、一人何役も演じる。小柳、佐川、鈴木の3人が演じる青年たちは、それぞれ父にまつわる傷を持っているが、彼らは名作『オイディプス王』『ハムレット』『白痴』を下敷きにした登場人物だ。この3作は観劇前にあらすじだけでも知っていると、3人の登場人物像と共により『岸 リトラル』の世界が深まるだろう。また大谷、栗田らベテラン俳優が、ウィルフリードらの旅の導き手のように、舞台を支えていく。

作者ムワワドが生まれたレバノンは、1975年に内戦が勃発した。収束する1990年までの15年の間に、20万人とも言われる人々が亡くなった。ムワワドの、戦争の真っ只中を生き幼いころフランスへ亡命、カナダへ移住した経験が、作品にも色濃く反映されているのだろう。
28歳の時に書かれた今作は、若さと熱気がほとばしる脚本ながら、親、世界、それをも越えた“生と死”が入り混じる奥深い世界観だ。演出の上村がそれを丁寧に、そして幻想的に見せていく。休憩を含む約3時間半の上演も長くは感じない。

照明、美術、音響、衣裳などの繊細で大胆なスタッフワークと上村の演出によって、何層にも重なる物語の構造は、時に何度も殻を破りながら一つにまとまっていく。コミカルなシーンも多いが、時おり劇中で語られるのは、日本人が耳にしてきた戦争とはまた違う、内戦による凄惨な記憶たち。けれど、俳優たちの身体を通して聞くと、どこかで知っている気がする。

「父さんをふさわしい場所に埋葬する」。そのために生と死、現実と幻想を行き来する旅を経て、死にたくない父と生きる気力のない息子は、どこにたどり着くのか。そして、戦争で死んだたくさんの人々と、現代を生きる私たちは何を葬り、何を握りしめて行くのか。父と息子という個人的な家族の物語を越えて、過去と未来、遠くの国と国とが、舞台の上で結びついていく。
『岸 リトラル』は、3月11日(日)まで東京・シアタートラムで、3月17日(土)に兵庫・兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホールにて上演。
(取材・文/河野桃子、写真/細野晋司)