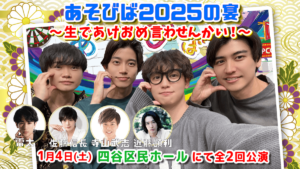7月22日(金)から24日(日)までの3日間、上野・東京文化会館にて東京バレエ団『ベジャール・ガラ』が上演された。20世紀最高の振付家と称される巨匠モーリス・ベジャール作品のレパートリー化40周年を記念して企画された本公演。この記事では、その3日目の模様をレポートする。
1982年の「ボレロ」初演以来、ベジャールがバレエ団のために創作した「ザ・カブキ」(1986)、「舞楽」(1988)、「M」(1993)を含む、累計22にも及ぶ傑作を踊り継いできた東京バレエ団。今回の『ベジャール・ガラ』では、ベジャールの三大傑作のひとつとされ、なんと9年ぶりの上演となった「火の鳥」をはじめ、「バクチIII」「ロミオとジュリエット」「ギリシャの踊り」の4演目が披露された。
東京バレエ団『ベジャール・ガラ』公演レポート
「ギリシャの踊り」
地中海がテーマの「ギリシャの踊り」は、まるでキラキラと光を反射する穏やかな波のような、舞台上に散らばったダンサーたちの群舞からスタートする。プリエやアティチュード、腕の動きの弛緩が面白い。
二人の若者のパ・ド・ドゥを踊ったのは岡崎隼也と井福俊太郎。男性2人によるパートだが、雄々しさというよりも軽やかで晴れ晴れとした空気感が会場中に広がる。工桃子と山下湧吾によるはだしのパ・ド・ドゥでは、工の小柄な体格から繰り出される太陽のような弾ける元気のよさが印象的だった。政本絵美とブラウリオ・アルバレスは、陽気なだけじゃない、海風や色気をも感じさせる風格あるハサピコを披露した。
そして池本祥真は、冒頭からしなやかで美しいジャンプなどで観客を魅了。どことなくギリシャの彫刻などをイメージさせる動きも印象的なソロのパートでは、軽快ながらも説得力が感じられる素晴らしい踊りを見せてくれた。

その他、次々に舞台上を埋め尽くす群舞も見どころの本演目。分かりやすい舞台装置やマイムは用いておらず、ダンサーたちの衣装も白と黒のみで何の装飾もない。それなのに、ギリシャ、豊かな地中海、燦燦と照らす太陽、大地の鼓動、頬を撫でる風、生命の呼吸などを、観客の想像力の中にありありと投影させるベジャールの表現の世界には感服だ。
「ロミオとジュリエット」
反戦のメッセージを掲げるベジャール版「ロミオとジュリエット」のパ・ド・ドゥを踊ったのは足立真里亜と樋口祐輝。東京バレエ団がYouTubeにアップしているインタビュー動画の中で、足立は本作について「周りで起こっている争いや命のやりとりの中に、私たちの普遍的な愛があるイメージ」と語っていた。アクロバティックで難しいリフトがたくさん出てくるが、それを感じさせない確かな技術力と、それによって表現される若者同士の瑞々しく勢いのある恋愛や争いの愚かさ。ベジャールがシェイクスピアから引き継いだ、「若者たちよ、争いをやめて恋をせよ」というメッセージは胸に迫るものがある。

「バクチIII」
現役バレエダンサーの中で、人気・実力ともに日本バレエ界のトップに君臨する二人による「バクチIII」。この演目を一番の楽しみにしていた観客も少なくないだろう(かく言う私もその一人だ)。ベジャール自身から直接指導を受けたこともある上野は、長い手足や甲の出た美しいつま先を存分に魅せた彼女ならではの貫禄あるシャクティを演じた。パートナーの柄本も、タブラの独特な音色にのせ、破壊と再生の神シヴァを体現。匂いたつような雰囲気に包まれての二人の競演は見ごたえ充分だった。

「火の鳥」
灰色の衣装を纏ったパルチザンたちの中から登場する、タイトルロール火の鳥を演じたのは大塚卓。燃え盛るばかりではなく、パチパチと心地の良い音を立てたり、優雅に揺らめいたり、じんわりと人を温めたり、暗闇を照らす優しい灯りとなったり、様々な“火”が表現される。パルチザンたちと円になって座った火の鳥が、自らの手の平に口づけをして隣の者と手を合わせる。その動きが繰り返され、ぐるっと一周回って火の鳥の元に戻ってくるところは短いながらも印象的で胸を打つシーンだ。
ストラヴィンスキーの「火の鳥」と聞いて思い出す、あのけたたましいような音楽が始まると、振り付けも激しさを増し、やがて火の鳥は地面に倒れてしまう。そういう演目だと知っていても、漠然とした不安に襲われる。しかし、再生したフェニックスを演じる柄本の姿を見て、なんだか心から救われるような気持ちになった。NHK教育テレビ「旅するフランス語」に出演していた際、柄本からは飾らない素朴な青年という印象を受けたが、そこからは想像もつかないような堂々たる出で立ちであった。
演目のラストに向けて“希望”という言葉がじんわりと胸に浮かんでくる。国内外で悲しい事件が起き、普段の生活で小さく傷つくことがたくさんあるけれど、我々は希望を失ってはいけない。何度でも不死鳥のように立ち上がり、命を燃やすのだ。

何度も何度も繰り返されたカーテンコール。大塚が上手袖に向かって手を差し出すものの、なかなか舞台上に姿をみせないある人物。少しの押し問答(?)を経て、照れくさそうに小林十市が姿を見せた。本公演の指導の為に来日していた小林は、この度、モーリス・ベジャール・バレエ団のバレエ・マスターに就任。芸術監督のジル・ロマンから直々にオファーを受けたそうで、今夏の暮れにローザンヌ入りし、新作のリハーサルに取り掛かるという。
終演後にお手洗いに寄ったとき、とあるご婦人のグループに遭遇した。熱心に、興奮気味に、感動を語り合う彼女たち。ベジャールの遺した素晴らしい作品が日本のダンサーたちによって踊り継がれ、たしかに、観客の心に何かを届けたようだ。
さて、東京バレエ団はこの翌日の7月25日(月)より、『HOPE JAPAN 2022』と題して、ベジャールの最高傑作「ボレロ」や、今回も披露された「ギリシャの踊り」などを携えた、全国ツアーの真っ只中。さらに8月20日(土)、21日(日)には子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」、さらに10月の「ラ・バヤデール」など、今後も注目の公演が目白押しだ。
(文・取材/エンタステージ編集部 写真/Shoko Matsuhashi)
【公演データ】
東京バレエ団『ベジャール・ガラ』
2022年7月24日(日)14:00開演
「ギリシャの踊り」
音楽:ミキス・テオドラキス
ソロ:池本祥真
「ロミオとジュリエット」(パ・ド・ドゥ)
音楽:エクトル・ベルリオーズ
足立真里亜、樋口祐輝
「バクチIII」
音楽:インドの伝統音楽
上野水香、柄本弾
「火の鳥」
音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキー
火の鳥:大塚卓
フェニックス:柄本弾
モーリス・ベジャール(1927-2007)
バレエを“20世紀の芸術”として確立したフランスの振付家。哲学者ガストン・ベルジェを父に、マルセイユに生まれる。パリでダンサーとしてキャリアを開始、1949年にはストックホルムのクルベ リ・バレエに招かれる。初の振付作品はストラヴィンスキー音楽の『火の鳥』(1950)。パリに戻ると エトワール・バレエ団を結成、『孤独な男のためのシンフォニー』ほか精力的に作品を発表した。 1959年、ベルギー王立モネ劇場支配人モーリス・ユイスマンに招かれ、『春の祭典』を創作。翌年20世紀バレエ団を設立し、『ボレロ』を創作。その後、『現在のためのミサ』(1967年)、『火の鳥』 (1970)を発表。20世紀バレエ団は1987年にスイスに本拠を移し、ベジャール・バレエ・ローザン ヌに形を変えた。ダンス学校ムードラをブリュッセルに設立(1970)、1992年にはルードラをローザンヌに設立した。その後も『バレエ・フォー・ライフ』『くるみ割り人形』などを発表。東京バレエ団のために『ザ・カブキ』(1986)、『舞楽』(1988)、『M』(1993)を創作している。勲三等旭日中綬章 (1986)、ベルギーのコロナ勲章(1988)、高松宮殿下記念世界文化賞(1993)等を授与される。2007年11月22日、最後の作品『80分間世界一周』の創作中、ローザンヌにて死去。