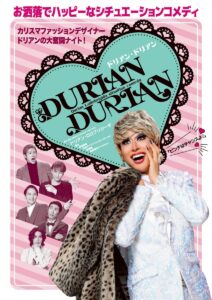2018年7月20日(金)より東京・THE POCKETにてStudio Life Next GENERATION『カリフォルニア物語』が幕を開けた。原作は「吉祥天女」、「BANANA FISH」、そして「海街 diary」と数々の名作を生み出してきた漫画家・吉田秋生の初期の代表作。スタジオライフが同作を舞台化するのは 2008年の初演以来、10年ぶりとなる。そんな思いの詰まった本作のオフィシャルレポートをお届けする。
【あらすじ】
物語は、主人公・ヒースが故郷のカリフォルニアを捨てて、ニューヨークのマンハッタンに辿り着いたところから幕を開ける。幼い頃に両親が離婚。母の愛を知らず、厳格な父のもと、優秀な兄と比較されて育ったヒースにとって、故郷のカリフォルニアは、孤独と反抗の街。誰もが憧れる広大な青空も、肥沃な大地も、ヒースの記憶の中では暗い灰色に塗り替えられていた。
自由を求めてやってきたニューヨーク。その道中のテキサスで、ヒースはイーヴという少年と出会う。ニューヨークで生まれ育ったイーヴは、ヒースとは反対に、明るいカリフォルニアに楽園を夢見ていた。カリフォルニアに焦がれるイーヴは、カリフォルニア出身のヒースにくっつくようにしてニューヨークへ逆戻り。ふたりは共同生活を送ることとなる。

この『カリフォルニア物語』は、屈折した心を抱えたヒースが、イーヴやその他の仲間たちとの出会い、そしてニューヨークでの暮らしを経て、大人の階段をのぼる成長物語だ。だが、成長には痛みが伴う。人は自ら傷を負い、血を流し、涙の苦さを味わうことで、少しずつ大人になっていく。1978年、つまり今から40年も前に連載を開始した『カリフォルニア物語』が今なお人の心を打つのは、そこに青春の光と影という普遍性が色濃く描かれているからだ。
10代の多くは、自分の痛みには敏感であるにもかかわらず、他人の痛みに関しては無自覚だ。自分の何気ない言葉や振る舞いが、大切な人を深く傷つけているかもしれない。そんな些細な想像が及ばないのが、10代の無邪気さであり、無神経さだ。決してそれは責められるべきものではない。なぜなら、みんな精一杯なだけだから。主人公のマスコミ関係各位ヒースも、そんなアンバランスな10代のひとりだ。

ヒースは、常に愛を乞うていた。その理由は、愛に飢えた生育環境にある。父に抱いたのは反発心。兄に覚えたのは劣等感。ヒースは家庭の中で自ら孤独の鎧を装った。兄嫁のスージーに恋心を寄せたのは、彼女が初めて人間的な温かさを向けてくれた相手だったから。新天地のニューヨークでスウェナと享楽的な恋に溺れたのも、愛されることが彼の充足感を満たす最善の手段だったからだろう。それは、何もヒースに限ったことではない。多くのティ ーンエイジャーが常に寂しさを持て余し、その空虚感を他者との交歓によって埋めるものだ。
だが、誰かの幸福の影に、誰かの涙や苦悩があるのもまた青春の必然。劣悪な家庭環境ゆえに一般的な教育を受けることさえできなかったイーヴは、他者から金品を盗むことと自らの身体を売ることでしか生計を立てられない。そんな過去との呪縛から解き放ってくれたのがヒースだ。ヒースとの出会いを経て、イーヴが過去の清算を遂げる。まるで兄弟のように仲良く暮らすふたりだが、やがてそれは新たなる孤独と寂しさの種となった。自分を救ってくれた相手が、いつしか自分を苦しめる相手となる。叶わぬ恋。言えない想い。開放的に生きるヒースの傍らで、自らの胸の内に笑顔という名の蓋をするイーヴがいじらしく切ない。
ヒースとイーヴ。性格こそ異なるが、ふたりは共に寂しさを持て余した子どもだったのだ。
スタジオライフは、そんなヒースとイーヴの関係を軸に、欲望渦巻くニューヨークの人間模様を生命感たっぷりに 描写した。特徴的な演出が、70~80年代アメリカを彷彿とさせるエネルギッシュな楽曲の数々だ。それだけで当 時青春を過ごした世代はもちろん、若い世代も自らの青春の日々を投影してしまう。

そして、そんな名曲に負けない瑞々しさを放つのが、役者陣だ。ヒースを演じる仲原裕之は、05年入団。イーヴの前では兄のような包容力を見せつつも、自らもまた完成されていない青年期の脆さを内包するヒースの複雑な心理を巧みに表現した。当初は自分自身のことしか見えていなかったヒースが、物語が進むにつれて、他者のために行動を起こす。その誠実さは、やがて暴走を生む引き金となるのだが、それだけ盲目的になれるのもまた若さの特権。仲原の豊かな感情表現が、ヒースの人間的な魅力を膨らませた。
対するイーヴを演じるのは、13年入団の千葉健玖(Wキャスト。Leafバージョンでは、12年入団の若林健吾が務 める)。不幸な生い立ちにもかかわらず笑顔を忘れないイーヴに、千葉の持つ透明感がマッチ。その無垢さは、まるで天使のようだ。折々に見せる苦悩の場面も押しつけがましさがなく、つい肩入れしたくなる。物語の構造上、イーヴの清新さが作品の印象を決めると言っても過言ではないが、その大役を若手の千葉が見事になし遂げた。

作品全体の印象としても、デリケートな問題を扱っていながら、決して重くなりすぎず、コミカルなシーンも挟まれていて、軽やかな仕上がり。あらすじだけ追うと、決して爽快な結末とは呼べない。にもかかわらず、カリフォルニアの大地を駆ける風のような澄んだ余韻が残った。いくつもの喪失を知ったヒースは、ともすれば初めてニューヨークに訪れたときよりもずっと孤独になったようにも見える。だが、決してそんなことはない。なぜならもう寂しさを持て余していた子どもではないから。
ヒースは、ずっと愛を乞うてばかりいた。でも、愛は自分のすぐそばにあった。そのことを知り、彼は大人になった。捨てたはずの故郷・カリフォルニアは、大人になったヒースにとってはどんな場所に見えるのだろうか。いつか再びヒースがカリフォルニアに帰ってきたとき、彼はどんな顔をしているのだろうか。終演の暗転の中で、そんなことを想像していた。
Studio Life Next GENERATION『カリフォルニア物語』は7月20日(金)から8月5日(日)まで上演。
(文/横川良明、写真/オフィシャル提供)