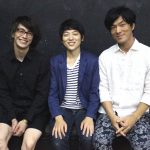2016年8月10日(水)、長塚圭史の名作を松居大悟が演出した舞台『イヌの日』が幕を開けた。会場は、東京・ザ・スズナリ。定員170席ほどの小空間が、15年間の監禁を描いた本作によく合っている。出演は尾上寛之や玉置玲央ら30歳前後の役者が意図的に集められた。30歳の松居をはじめとした同世代だけによる『イヌの日』ができあがっている。
(※以下、作品の内容に関する記述あり)

広瀬(玉置)の部屋では、いつものように友達の中津(尾上)らがバカ騒ぎをしている。このメンバーがどうしようもない。酒を飲んでは水をかぶったり、服を脱がせ合ったり、勝手に冷蔵庫の中のものを食べたりと大暴れ。恋愛のグチなども聞かされ、家主の広瀬はどうにもやりきれない。しかし突然、中津が広瀬に頼み事をしたことで、事態は思わぬ方向へと進んでいく。

広瀬が中津に連れられてやってきたのは、防空壕の跡地。暗い地下には、広瀬と同い年くらいの孝之(目次立樹)、菊沢(青柳文子)、洋介(大窪人衛)、柴(川村紗也)が暮らしていた。中津に「地上は大気汚染で地獄のようになっていて、おまえらの親も全員死んだ。外に出ると危ない」と言い聞かされ15年間も防空壕に住む彼らは、つまり、中津に監禁されているのだ。

「1ヶ月留守にする」という中津は、広瀬に無理やり200万円もの大金を渡し、4人の食事の世話を頼む。わけもわからないままに引き受けてしまった広瀬を後に、中津はなにやら大荷物を抱えて出て行く。

15年間外に出ず、大人にも触れずに生きてきた4人は、言うこともやることも、一つひとつが子どもっぽい。「保存ごっこ」と称し、動物の泣き声や飲み物を飲むゴクリという音など、いろんな音を出して遊んでいる。普通に成長した大人であれば「なにが楽しいの?」と思うようなことをして全力で遊んでいる様子は、ともすれば大人の役者が子ども役を演じているように見えてもおかしくない。けれども、“子どものまま体が大きくなった大人”という奇妙な存在に説得力があるのは、それぞれの演技力が非常に高いからだろう。

登場人物のなかで唯一まともに見えるのが、玉置演じる広瀬。わけもわからず巻き込まれ、右往左往するそのポジションが、観客はもっとも感情移入しやすい。けれども広瀬は、自分の意志のないまま流されていく。監禁という状態に目をつぶり、その状況に染まっていく。しかし時には「外に出よう」などと正義感を口にする。その姿は、無責任で口だけの人間だ。そしてそういう人間は、現実の世界でも少なくない。広瀬に感情移入することで、自分の醜さや偽善を突きつけられたようで息苦しくなる。

ヒロイン・・・と呼んでもいいのだろうか、青柳演じる菊沢の存在が物語のキーとなる。彼女の舌足らずな喋り方と、邪気のない行動、悪気のない素直さは、聖女のようでありながら悪の原石のようでもある。監禁された他の3人はまだ善悪に対して敏感だが、菊沢だけは、善にも悪にも等しく距離をとっている。観終わったあと、彼女の存在がどう見えているかに、その人の善悪に対する見方が表れていそうだ。

すべての登場人物が、見事にカラーが違う。それぞれの思いのベクトルが異なっているため、どの人物もキャラクターが立っている。長塚が意味を与えた役を、役者それぞれが生き、演出の松居がそれぞれの存在価値を輝かせている。演出・役者の力量が高いこともそうだが、なにより脚本の土台がしっかりしている。長塚の阿佐ヶ谷スパイダースにおける名作と言われるのも納得だ。

今回の上演にあたり、長塚が新たに脚本を書き直している。そもそも2000年の初演と2006年の再演では、それぞれ登場人物をはじめ異なる点が多い。今回は両方の要素を混ぜ、また新しい『イヌの日』ができあがっている。
当初は、2000年に発覚した新潟少女監禁事件をもとに書かれたという本作。あえて30歳前後のキャストだけで上演したことで、この世代のリアルな感覚が浮き立つ。登場人物の誰もが、意図しないままに自分が楽な方へと進んでいく。その在り方は、現代の危機を思わせるようでもあった。
舞台『イヌの日』は、8月21日(日)まで、東京・ザ・スズナリで上演。
(取材・文・撮影/河野桃子)