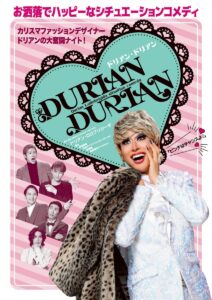舞台『管理人』が11月26日(日)に東京・シアタートラムにて開幕した。本作は、ノーベル文学賞作家ハロルド・ピンターが1959年に書き上げ、1960年にロンドンで初演された名戯曲。今回の上演では、森新太郎のエッジの効いた演出、徐賀世子による切れ味鋭い新訳、そして、溝端淳平、忍成修吾、温水洋一という絶妙にアンバランスな3名の出演者により、息が詰まりそうになる人間関係の中に、緊張感の中に漂う滑稽さ、それゆえの切なさが浮かび上がる。
演出の森、出演者の溝端、忍成、温水より、初日を迎えた心境や役の魅力についてのコメントが届いたので紹介する。
◆森新太郎(演出)
初日を迎えて、改めてピンターは人間の愛というものを描きたかった作家なのではという気がしています。稽古中、字面だけでは分からなかった役の関係性が俳優を通して立ち上がってきて、それがあまりに切なくて、こんなに哀しいのかと感じました。1960年ロンドン初演の作品ですが、さすがにピンターだけあって普遍的な人間の痛みを描いていて、いつの時代にやっても突き刺さる人には突き刺さる作品。のめり込んでしまう人は兄弟やデーヴィスの過去、この先のことなど、どんどん気になって引き込まれて、抜け出せなくなるのでは。
出演者3人は完璧な顔合わせです。温水さんは飄々としながらもまわりに意識をビシッと張り巡らせ、忍成くんは圧倒的な集中力で彼の世界をつくり、溝端くんは華があり、そこからとてつもなく深い闇を垣間見せてくれて、僕が想像した以上にそれぞれ見事に役を膨らませてくれました。
僕は気分が塞がっている時にこの作品を読んだらおもしろく感じたのですが、同じくちょっと気分が塞がっていたり、人生に行き詰っているかもと思う人に観てもらえたら「人間ってこうなのかもな」と、救われた気持ちになるかもしれません。人生にどん詰まっている方にこそ、ぜひぜひ観ていただきたい舞台です。

◆溝端淳平(ミック役)
抱えてきたものをお客さんに観てもらえる初日はワクワクして楽しかったです。ピンター作品は一筋縄ではいかないとは覚悟していましたが、森さんの飽くなき探究心や何かを掘り出そうという執着心に魅せられて、稽古を積み重ねてきて、培ってきたものを出すことができました。答えを提示するのではなく、お客さんの想像力をかき立てる、如何様にでも解釈できるところがこの作品の魅力で、僕も演じていて毎日発見があります。ミックは「異物」だと思っているのですが、異物として舞台に出る感覚、支配している感覚というのは、演じていてとても楽しいものだと思いました。

◆忍成修吾(アストン役)
僕が演じるアストンだけでなく、ミックもデーヴィスも、この戯曲自体が本当におもしろくて、全部繋がっているように思うんです。でも「これってもしかして・・・」という発見を、あえて皆で共有しないで、それぞれがこっそり持っている。森さんの策略なんだと思います。森さんはギリギリの高さの階段を一段ずつ用意してくれて、ようやく登れたと思ってもさらに上に階段がある。考え方によっては苦しいですけど、食らいついていけばだんだんハイになって楽しくなってきます。そして、今いる所から最初の自分を見下ろすと、すごく高くまで登っていることに気付くんです。これからも森さんの演出を信じていきたいと思います。

◆温水洋一(デーヴィス役)
2年ぶりの舞台なのですが、これは相当手強いぞ、と。初日が終わった今の気持ちは、これまでの作品で感じたことのある初日の解放感とかではなくて、ふわふわしているというか、こんな感覚になったのは初めてかもしれないです。お客さんが一つの部屋を覗き見しているようなお芝居で、デーヴィスは出番も台詞も多いのですが、でも大変さは3人とも同じ。森さんとも話して、「無様」が似合う奴を演じようと最初から決めていましたが、もっともっと無様でも良い。そんな無様で憎たらしいデーヴィスを演じることも楽しみたいですね。
『管理人』は、12月17日(日)まで東京・シアタートラムにて上演。

(撮影/細野晋司)